【個人事業主の開業手続】青色申告と白色申告の違い、配偶者も関与する場合についてもまとめて解説
- 正俊 矢尾
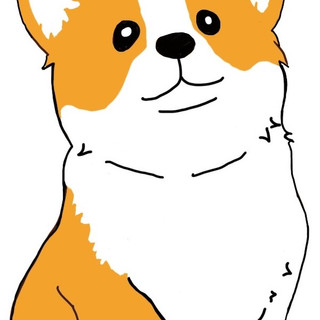
- 2025年4月30日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年4月30日
これから個人事業主として事業を始めようと考えている方へ。開業には、最低限押さえておくべき手続きがいくつかあります。
この記事では、開業の基本手続き、青色申告と白色申告の違い、配偶者が事業に関わる場合の選択肢まで、わかりやすくまとめました!

個人事業主の開業に必要な手続き
個人で事業をスタートする場合、まず次の2つの書類を税務署に提出する必要があります。
1. 開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)
提出期限:事業開始から1ヶ月以内
提出先:事業所の所在地を管轄する税務署
主な内容:事業の概要、事業開始日、事業所所在地、職業など
開業届を提出することで、正式に「個人事業主」として認められます。
提出しなくても違法ではありませんが、青色申告の特典を受けられなくなるので注意が必要です。
2. 青色申告承認申請書(希望する場合のみ)
提出期限:開業届を提出する年の3月15日まで(もしくは開業日から2ヶ月以内)
主な内容:帳簿の付け方、承認を受けたい所得の種類など
後述する「青色申告」をしたい場合は、必ずこの申請書も出しておきましょう!
青色申告と白色申告の違い
青色申告とは?
正しい帳簿(複式簿記など)をつける代わりに、税務上大きなメリットを受けられる制度です。
主な特典:
最大65万円の所得控除(簡易簿記の場合は10万円控除)
赤字の繰越(最大3年間)が可能
専従者給与制度(後述)を使える
白色申告とは?
簡単な帳簿づけでOKですが、控除や特典がほとんどありません。
どちらを選ぶべき?
→ 基本的に事業を行うのであれば、青色申告がおすすめです!
特に会計ソフトを利用して複式簿記で記帳しているにも関わらず、白色申告のままとされている事業者の方もたまに見受けられます。
所得控除幅として最大で55万円の幅がありますが、当該金額を支出無しで経費処理できるような効果がありますので、悩むまでもなく青色申告をお勧めさせていただいております。
配偶者が事業を手伝う場合の選択肢(扶養 vs 青色事業専従者)
事業を配偶者に手伝ってもらう場合、次の2つの選択肢で悩まれる方が多い印象があります。
1. 配偶者を「扶養」に入れたままにする場合
配偶者に給与は支払わないか、年間給与を103万円以内に収める
配偶者控除(または配偶者特別控除)が受けられる
配偶者自身も税金や社会保険料が発生しにくい
こんな場合におすすめ:→ 配偶者の関与度が低い、あくまで「手伝い」程度の場合
2. 配偶者を「青色事業専従者」として給与を支払う場合
青色申告をしている個人事業主に限り、配偶者に支払う給与を必要経費にできる
年間に支払った給与額を経費にできるため、事業主側の所得を圧縮できる
要件:
配偶者が原則として事業に専従していること(週30時間以上が目安)
他にパートなどをしていないこと
こんな場合におすすめ:→ 配偶者が事業にしっかり関与し、フルタイムに近い形で働く場合。
青色事業専従者にする場合の手続き
もし配偶者を「青色事業専従者」として給与を出す場合は、次の書類も必要です。
青色事業専従者給与に関する届出書
提出期限:3月15日まで(または開業日から2ヶ月以内)
税務署に提出
給与額は「労務の対価として適正な金額」である必要があり、実態にそぐわない高額な設定は認められません。
【まとめ】個人事業主の開業手続きのポイント
開業届は必ず提出しよう
できれば青色申告承認申請書も提出しておく
配偶者が事業に深く関与する場合は、「扶養に残すか」「青色事業専従者にするか」慎重に選ぶ
個人事業主の開業は、最初の手続きを間違えると後で大きな税負担差が出ることもあります。不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします!
個人事業主、法人どちらの場合で開業する際でも、必要な手続きについては、freeeやMoney Forward、弥生といった会計ソフトメーカーでも書類作成を無料で簡単にできるサービスが展開されていますので、そちらをご利用いただくと安価かつ簡単に開業することができます。
当事務所では、開業サポートから青色申告手続き、専従者制度の活用まで一括支援しております。お気軽に無料相談をご利用ください!


コメント