【開業前必読】スモールビジネスのための収支計画ガイド
- 正俊 矢尾
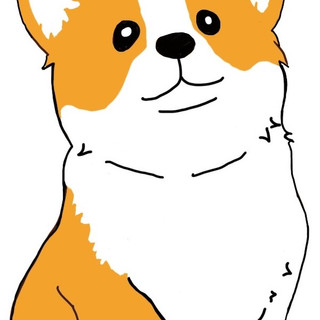
- 2025年4月30日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年5月3日
スモールビジネスの開業を考えるとき、「どれくらい稼げればよいのか?」「いつ黒字化するのか?」といったことがぼんやりしたまま進んでしまうケースは少なくありません。しかし、売上や費用を事前に想定して収支計画を立てることで、事業の継続可能性や資金繰りの限界が見えるようになります。
このコラムでは、法人として飲食店を始めるケース、個人事業主としてコンサルティングを行うケース(月商100万円規模)を例に挙げて、初心者にもわかりやすく「収支計画」の作り方と、数字の考え方を解説します。

1. 収支計画とは?なぜ必要なのか
収支計画とは、「毎月いくら稼ぎ、いくら使い、いくら残るか」を数値で想定することです。以下のような目的で使われます:
売上目標や価格設定の根拠をつくる
いつまでに黒字化できるかを把握する
赤字でも事業継続できる運転資金を確保する
融資・補助金の審査で必要な資料になる
2. 収支計画の基本構成と実例
【例1】法人で小さな飲食店を開業する場合
売上
客単価:1,200円 × 1日30名 × 月25日営業 = 月商90万円
原価(食材費)
目安は売上の30%前後:90万円 × 30% = 27万円
販管費(固定費・変動費)
固定費:家賃15万円、人件費30万円、水道光熱費5万円、通信費1万円、保険料2万円 = 月53万円
変動費:カード手数料・広告費などで売上の5% → 5万円
営業利益
90万円 − 27万円 − 53万円 − 5万円 = 10万円
【例2】フリーランスでコンサルタントを行う場合
売上
顧問契約(20万円 × 4社)+スポット案件(20万円 × 1件) = 月商100万円
原価
基本的に人的コストのみ。実費としては:
交通費・資料印刷等:約1万円
業務用ソフト:Office 365、Notion、Zoom 等:約1万円
会計ソフト(freeeやMFクラウド):3,000円/月
パソコン減価償却費(月割で想定):約1.5万円 → 合計で 約4万円
販管費
固定費:
通信費(モバイル・Wi-Fi):0.7万円
サブスク・クラウド管理:0.3万円
書籍・研修費:1万円
自分の報酬的生活費:30万円 → 合計32万円
変動費:
外注(リサーチ・翻訳補助など):1万円
会議費:1万円
広告・交流会・紹介料等:2万円 → 合計3万円
営業利益
100万円 − 4万円 − 32万円 − 4万円 = 営業利益60万円
※ 個人事業主であるため、ここから所得税・住民税・国民健康保険・年金等が差し引かれます(年間150〜200万円程度想定)
3. 固定費・変動費の例(事業形態別)
項目 | 飲食店(法人) | コンサルタント(個人) |
|---|---|---|
家賃 | 店舗賃料(月15万〜) | 自宅の一部按分(0〜3万円程度) |
人件費 | アルバイト・社員給与 | 基本なし、自分の報酬扱い |
水道光熱費 | 店舗運営に応じて高い | 自宅と共用、数千円程度の按分 |
通信費 | レジ・ネット回線 | Zoom・スマホ等(7,000円前後) |
ソフトウェア | POS/レジ連携ソフト等 | 会計・業務管理・資料作成等で1万〜2万円 |
広告費 | チラシ、食べログ、Google広告 | note・SNS広告・紹介報酬など |
減価償却 | 厨房設備など | パソコン・モニターなど |
4. 「安全・許容・危険」水準の目安
観点 | 安全水準 | 許容水準 | 危険水準 |
|---|---|---|---|
営業利益(月) | 30万円以上 | 10〜29万円 | 10万円以下、または赤字 |
固定費カバー月数(資金) | 6ヶ月以上 | 3ヶ月前後 | 1ヶ月未満 |
売上総利益率(粗利率) | 60%以上 | 40〜59% | 39%以下 |
5. 数字の「置き方」=仮説の立て方
ここでは、飲食店(月商90万円モデル)を例に、売上・原価・固定費・変動費などの数字をどのように置けばよいかを、段階的に説明します。数字の立て方は感覚ではなく、「仮説」と「根拠」をセットで考えることが大切です。
(1)売上の仮説を立てるには?
例:月商90万円の根拠の作り方
客単価:1,200円(近隣競合のランチ・ディナー価格帯を調査)
客数:1日30人と仮定(近隣人口、店の座席数、回転数、通行量などを観察)
営業日数:月25日(定休日週2日)
→ 1,200円 × 30人 × 25日 = 90万円
仮説の裏付けとして見るべきもの:
同エリアの人気店・空いている店の混雑具合(席数・回転数)
食べログなどでの単価と来客数のレビュー
予備テスト営業・プレオープンで実測した日商
(2)原価(仕入れ)の仮説を立てるには?
飲食店の場合、原価率は30〜35%が目安(原材料費+廃棄+副材料を含む)
実際のメニューを数品ピックアップし、1食分あたりの食材コストを出してみる
例:日替わり定食
米80円、魚220円、副菜100円、調味料30円 → 原価430円
販売価格1,200円 → 原価率35.8%(やや高め)
→ 定番メニューと原価率の低いサイドメニュー(ドリンク・デザート)で全体原価を30%程度に抑える
(3)固定費の仮説を立てるには?
固定費は「売上に関係なく毎月必ず発生する支出」です。
家賃:立地・坪数×坪単価、相場を不動産サイトで確認
人件費:必要人数×時給×シフト時間数(社会保険なども含む)
水道光熱費:厨房・空調の電気代、水道代(同業からヒアリング)
通信費・保険・会計ソフト:月額契約金額を元に見積
例:
家賃:15万円(10坪 × 1.5万円)
アルバイト2人:時給1,100円 × 6時間 × 25日 × 2名 → 約33万円 → 社保調整やシフト圧縮で20万円に抑制
水道光熱費:平均5万円(夏冬は上振れあり)
→ 合計43万円が固定費仮説
(4)変動費の仮説を立てるには?
変動費は「売上に応じて増減する費用」です。
カード決済手数料:3〜5%(Airペイ・Squareなど)
広告費:食べログ有料掲載、チラシ配布、SNS広告など
配送/テイクアウト容器費用(導入していれば)
例:
90万円売上 × 決済手数料5% → 4.5万円
→ 予算として「売上の5〜8%」を目安に変動費を見積もるとバランスが取れやすい
(5)精度を上げる工夫
数字は「最小値」「平均値」「最大値」のレンジで用意して、現実的な中間値を採用
月別で計画し、繁忙期(年末年始、GW)と閑散期(2月、8月等)を加味
検証のたびに仮説をアップデートする前提で作成
6. まとめ|収支計画は「数字で経営する」第一歩
収支計画は、事業の方向性と持続性を可視化することができます。
数字はあくまでざっくりした見込みですので、完璧でなくてよいです。ただし「なぜそう考えたか」は根拠が重要です。
法人・個人問わず、まずは月単位で「売上−原価−経費」のモデルを組み立てることが重要です。
収支では黒字でも場合によってはお金が足りなくなることもあります。収支計画と合わせて資金繰り計画も作成してみると、経営をより具体的に考えることができます。



コメント